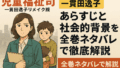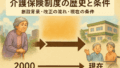「介護保険って、結局誰が申請できるの?」——そんな疑問を抱えていませんか?要介護認定を受けている全国の利用者は約690万人。特に【65歳以上】のすべての高齢者と、【40~64歳】でも特定疾病(16種類)の方が申請対象となります。しかし、実際に制度を活用している人は全体の約3割。多くの方が「自分や家族は該当するのだろうか…」「申請にはどんな書類が必要?」と不安を抱え、手続きを先延ばしにしがちです。
また、2024年から手続きの一部がオンライン化されるなど、制度も常に変化し続けています。知らずに放置してしまうと、必要なサービスを受けそこねて「日常生活で困難を感じ続けるリスク」すらあります。
そんな心配を「今、ひとつずつクリア」にしませんか?申請の条件や具体的な準備、誤解しやすいポイントや注意点まで、最新の法改正動向も交えながら専門家の視点でわかりやすく解説します。本文を読み進めるだけで、ご自身・大切なご家族にとって本当に必要な介護保険サービスを、しっかり使いこなせるようになります。
介護保険を申請できる人とは?基本の理解と制度概要
介護保険制度の基本構造と目的をわかりやすく解説
介護保険制度は、高齢社会に対応するための社会保険制度で、介護が必要となった人が自立した生活を送るための支援を目的としています。40歳以上の国民が加入し、負担を分かち合いながら介護サービスを受ける仕組みです。保険料は年齢や所得によって異なり、市区町村が保険者となってサービスを提供しています。認定を受ければ、介護サービスの自己負担が原則1〜3割となります。介護の必要性が増す現代社会において、生活の質を維持する重要な制度となっています。
申請できる人の全体像と基本条件
介護保険の申請ができる人は年齢や健康状態によって明確に定められています。主な対象者は、以下のように分類されます。
| 区分 | 対象者 | 申請要件 | 特記事項 |
|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 加齢に伴う要介護・要支援状態 | 病気(特定疾病以外)や認知症など多様な原因が対象 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳 | 16種類の特定疾病による要介護・要支援状態 | 特定疾病の発症のみが対象(例:がん末期、認知症、脳血管疾患など) |
申請には「介護保険要介護認定申請書」や被保険者証などが必要です。市役所・町村役場窓口や郵送、代理人申請も可能です。入院中でも申請はでき、家族や担当ケアマネジャーが代行する場合もあります。
申請できる人の範囲を取り巻く最新動向
介護保険申請の対象範囲は法改正や社会ニーズに応じて見直されています。特に40〜64歳の方は、該当する16の特定疾病(脳血管疾患、がん末期、初老期認知症など)に罹患し要介護状態となった際のみ申請が可能です。特定疾病の詳細一覧および診断基準は厚生労働省で最新情報が随時公開されています。代理申請が認められており、家族やケアマネジャーによるサポート体制も拡充されています。ここ数年は、入院中や退院直後の申請も増え、行政窓口のサポートや書類請求のオンライン化も進んでいます。申請しない場合、介護サービス利用ができず、費用面・生活面での負担増になることが多いため、早めの相談と手続きが重要です。
介護保険申請の年齢基準と特定疾病の詳細
介護保険を申請できる人には年齢に応じた基準があります。主に次の2つの区分に分かれます。
-
65歳以上(第1号被保険者):
- 年齢が65歳以上であれば、病気や状態に関わらず要介護・要支援状態と認められれば申請が可能です。
-
40歳以上64歳未満(第2号被保険者):
- 医療保険に加入しており、かつ厚生労働省が定める16種類の特定疾病を原因として要介護・要支援状態となった場合のみ申請できます。
申請は市区町村の窓口、またはケアマネジャー等による代理申請も認められています。
申請タイミングとしては、日常生活で継続的な介護や支援が必要と感じ始めた時点が目安です。早期の申請がサービス利用開始までの期間短縮につながるため、迷った場合は自治体窓口や地域包括支援センターなどで相談しましょう。
年齢別申請条件と申請可能なタイミング
年齢ごとに申請の条件が異なり、それぞれ注意が必要です。
| 年齢区分 | 被保険者区分 | 申請できる条件 | 申請の流れ |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 第1号被保険者 | 年齢要件を満たせば原則誰でも申請可能 | 市区町村窓口で申請 |
| 40歳~64歳未満 | 第2号被保険者 | 医療保険加入+特定疾病が要介護・要支援の原因である場合 | 市区町村窓口で申請 |
| 申請代理人 | 家族、成年後見人他 | 本人が申請困難な場合に代理申請も認められている | 必要書類(委任状など)を提出 |
申請のタイミングは、急変や入院、退院後の在宅介護開始時などが多い傾向です。入院中も申請は可能で、必要な場合は代理人が手続きを進めます。65歳の誕生日を迎えた時点で、要介護状態であればすぐに申請できる点も重要です。
16特定疾病の具体一覧と診断基準
40歳以上64歳未満の方が介護保険の対象となるには、下記の16特定疾病が原因で要介護・要支援状態になっていることが必要です。各疾病は医師による診断書・意見書により認定されます。
| 疾病名 |
|---|
| がん(末期) |
| 関節リウマチ |
| 筋萎縮性側索硬化症(ALS) |
| 後縦靭帯骨化症 |
| 骨折を伴う骨粗しょう症 |
| 初老期における認知症 |
| 進行性核上性麻痺 |
| 多系統萎縮症 |
| パーキンソン病関連疾患 |
| 脊髄小脳変性症 |
| 脊柱管狭窄症 |
| 早老症 |
| 多発性筋萎縮症 |
| 糖尿病性神経障害、腎症、網膜症 |
| 脳血管疾患 |
| 閉塞性動脈硬化症 |
これらに該当しない病気や外傷による介護状態では、65歳未満では原則として申請ができません。診断基準や詳しい書類については、医療機関や自治体の案内を確認しましょう。
特定疾病以外のケースと65歳未満の申請可能性
特定疾病に当てはまらない40歳~64歳未満の方は介護保険の申請はできません。65歳以上であれば、原因となる病名や状態を問わず、介護や支援が必要と認められれば申請が可能です。
【ポイント】
-
65歳未満:特定疾病による介護状態のみ申請可能
-
65歳以上:病名を問わず、要介護・要支援状態であれば申請可能
-
代理申請:家族やケアマネジャーなどが代行可能。委任状などが必要になる場合があります
入院中や施設入所中の場合も、必要に応じて本人または代理人が手続きを進めることができます。困ったときは地域包括支援センターや市区町村窓口へ早めに相談し、適切なタイミングで申請を行いましょう。
介護保険申請の必須書類と準備方法の徹底解説
介護保険を活用するには、正しい書類の準備と段取りが重要です。申請書類に不備があると認定が遅れるリスクがあります。ここでは申請に必要な書類や準備のポイント、最新の制度動向までをわかりやすく紹介します。申請する本人や家族だけでなく、代理申請にも備えた情報をまとめています。
申請に必要な書類の詳細リスト
介護保険申請時に求められる主な書類と内容は以下の通りです。申請に不備があると認定が遅れるため、記載内容や必要な添付書類をあらかじめチェックしておきましょう。
| 書類名 | 主な対象 | 内容・確認ポイント |
|---|---|---|
| 介護保険要介護・要支援認定申請書 | 全ての申請者 | 市区町村に提出する申請書類 |
| 介護保険被保険者証 | 65歳以上または支給対象者 | 被保険者の身分を証明する重要な書類 |
| 健康保険証 | 40歳以上65歳未満(第2号被保険者) | 特定疾病による申請の場合など |
| 特定疾病の診断書 | 該当疾病がある場合 | 医療機関による正式な診断書 |
| 印鑑 | 本人・代理人 | 申請書記入時などで使用 |
| 本人確認書類(運転免許証など) | 全ての申請者 | 氏名や住所の確認 |
| 委任状・代理人の本人確認書類 | 代理申請時 | 代理人が申請する場合に必要 |
書類ごとに提出先や証明内容が異なるため、事前に自治体ホームページや窓口で最新情報をチェックすることが大切です。
書類準備でのよくあるミスとその回避法
介護保険の申請書類は正確性が重視されます。以下はよくあるミスと、その回避法です。
-
書類の記入漏れや間違い
- 提出前に見直しを行い、記載内容が正確か確認しましょう。
-
必要書類の不足
- 必要書類は事前にリストアップし、不明点は役所に問い合わせしてください。
-
特定疾病がある場合の診断書未提出
- 特定疾病による申請時は診断書が必須です。医療機関の診断を早めに依頼しましょう。
-
代理申請の際の委任状忘れ
- 代理申請には委任状や代理人の身分証明書が求められます。
-
申請書の記載内容と実際の状況に相違がある
- 状況とズレがある場合は事前に福祉課等に相談して正しい申請を進めてください。
申請ミスを未然に防ぐためには、自治体から配布される申請ガイドやチェックリストを活用し、不安な場合はケアマネジャーや地域包括支援センターにサポートを依頼すると安心です。
マイナンバー連携による書類提出の軽減と今後の展望
現在、介護保険申請では一部自治体でマイナンバー連携が進んでいます。手続きの効率化や本人確認の簡略化が期待できます。マイナンバーカードを活用することで、健康保険証や身分証などの提出が省略される場合もあります。
今後は「マイナポータル」などのオンラインサービス活用がさらに拡大する見込みです。本人や家族の負担軽減のため、デジタルでのデータ連携や電子申請も進みつつあります。制度改正や自治体の最新情報をこまめに確認し、スマートな申請へ備えましょう。デジタル環境に不慣れな場合も、窓口や電話、ケアマネジャーのサポートを活用することで、安心して申請できます。
介護保険申請の手続き詳細と5ステップの流れ
介護保険の申請では、安心してサポートを受けるためにも、正確な手続きの流れを知っておくことが重要です。対象となる方は、原則65歳以上または特定疾病をもつ40~64歳の方です。申請には必要な書類や段取りがありますが、要点を押さえることでスムーズに進みます。
自然な流れで手続きを進めるために、以下の5ステップで全体像を確認してください。
| ステップ | 内容 | 補足 | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| 1 | 申請書類の準備・提出 | 市役所や地域包括支援センターへ書類を提出 | 保険証、申請書、本人確認書類 |
| 2 | 日程調整 | 認定調査員との面談日程を調整 | - |
| 3 | 認定調査 | 認定調査員が自宅・施設・入院中病院等を訪問 | 同居家族が同席可能 |
| 4 | 判定会議(一時・二次審査) | 調査結果をもとに審査判定 | 医師意見書も参考 |
| 5 | 結果通知・サービス利用開始 | 認定区分の決定と利用開始案内 | 認定通知書 |
申請可能な代理人や、入院中の申請も対応しており、年齢、病気の状況により必要な書類やフローに違いがあります。
申請書類の提出から認定調査までの流れ
申請は、本人や家族が市役所、または地域包括支援センターの窓口にて行います。介護保険証や健康保険証、本人確認書類などが必要になります。入院中の場合や体調不良の方には代理申請も可能です。例えば、家族やケアマネジャー、医療機関の相談員などが申請代行できるため、無理なく手続きを進めることができます。
提出後、市区町村の担当者と認定調査の日程調整が行われます。スムーズに進めるには、事前に必要書類を確認し、疑問点は窓口で確認することがおすすめです。
調査当日の流れと調査員からの質問例
調査当日は、調査員が自宅や入院先を訪問し、本人・家族に健康や日常生活動作の状況について質問します。主な質問例は以下の通りです。
-
日常生活動作(食事・排泄・着替え・入浴など)の自立度
-
認知症やもの忘れ、判断力の状態
-
病歴や既往症、特定疾病の有無
-
生活習慣や不安点、家庭でのサポート体制
調査は約1時間程度で終了します。正確に困りごとや支援の必要性を伝えることが、適切な判定につながります。面談には家族など同席者がいるほうが、実態を的確に調査員へ伝えやすくなります。
一次・二次判定プロセスの詳しい説明
認定調査が終わると、一次判定としてコンピューターによる自動評価が行われます。その後、二次判定では専門家と医師による審査会議が開かれ、調査結果や医師意見書をもとに要介護区分が決定されます。
ポイントとしては、特定疾病の場合は病名や診断基準の確認も必須です。入院中や65歳未満の場合には、病院の主治医の意見書も重要になります。
最終的に、「要介護1~5」「要支援1・2」「非該当」などの区分が記された認定通知書が約30日以内に届き、必要な介護サービスの利用準備が進められます。申請から利用開始までの流れを把握し、漏れなく手続きを済ませましょう。
代理申請・代行申請の実務と条件を専門的に解説
介護保険申請は、本人以外でも代理や代行による申請が可能です。体調不良や入院などで本人が申請できない場合、家族や親族、信頼できる第三者が手続きを行うケースが増えています。申請場所は主に市役所や区役所の介護保険窓口ですが、状況によっては郵送やケアマネージャーへの相談も選択肢となります。申請の際には本人の健康保険証や印鑑、身分証明書などが必要です。代理申請には適切な書類の提出と条件の確認が求められるため、制度の詳細を事前に理解しておくことが求められます。
代理申請が可能な人や条件の詳細
介護保険の代理申請は主に以下の方が行えます。
| 代理申請が可能な人 | 主な条件や注意点 | 必要なもの |
|---|---|---|
| 家族(配偶者・子など) | 本人の同意や委任状が望ましい。 | 委任状、健康保険証、代理人の身分証 |
| 施設職員 | 入所者に関する正当な理由がある場合 | 施設利用証明、委任状 |
| 友人・その他第三者 | 本人の事情が特にある場合のみ | 委任状、身分証明書 |
健康状態や意思能力に問題がある場合は特に、単なる申請だけでなく代理人の適格性や委任内容が明確に求められます。なお、65歳未満で申請する場合は特定疾病に該当するかも厳格に確認されます。
ケアマネージャーなど専門職による代行申請の現状と課題
ケアマネージャーは介護認定申請や区分変更申請のサポート役として、本人や家族を支援しています。実務においては、以下の課題が挙げられます。
-
申請書作成の負担軽減:書類作成や提出代行により、家族の事務負担が減少します。
-
行政窓口との調整:専門知識を活かして窓口とのやり取りが円滑に進むメリットがあります。
-
課題:
- 申請内容に齟齬があった場合、認定に影響するケースがあり、申請の精度が求められます。
- 代理人が実態を十分把握していない場合、誤情報で申請が進むリスク。
- ケアマネによる申請書の記載代行は自治体ごとで可否が異なる場合がある。
利用を検討する場合、本人の同意と最新の制度状況を必ず確認しましょう。
代理申請時のトラブル事例と防止策
介護保険の代理申請ではいくつかのトラブルが報告されています。具体的な事例と対応策を示します。
-
委任状の不備:書式や内容に不備があると申請が受理されません。提出前の確認が必須です。
-
本人確認書類の不足:健康保険証や身分証明書が揃わず、手続きが遅延する例が目立ちます。
-
代理人の資格不適正:親しい友人が無断で申請し、後でトラブルになることも。
【トラブル防止策】
-
申請前に必要書類をリストアップし、チェックリストを活用する
-
委任状や同意書は予め自治体の様式を確認し、正しく記入する
-
疑問や不安は事前に市役所や専門職に相談するのが安心です
このように、制度に沿った正確かつ丁寧な準備がスムーズな申請につながります。
介護認定調査の実態と申請者別の対応ポイント
介護認定調査では、本人の健康状態や生活状況を詳細に確認し、公平かつ正確な判定が行われます。申請者が家族や代理人の場合も、必要な事項を正しく伝えることが重要です。申請時に必要な書類や基本的な流れを理解し、要介護認定に向けてしっかりと準備しましょう。
下記のテーブルで申請者別のポイントをまとめています。
| 申請者 | 必要なもの | 対応ポイント |
|---|---|---|
| 本人 | 介護保険被保険者証、身分証明書 | 正確な生活状況や健康状態を説明する |
| 家族 | 委任状、家族の身分証明書 | 本人不在時は代理説明、生活環境把握 |
| 代理人(ケアマネ等) | 委任状、代理人の証明書、家族同意書 | 客観的に状況を伝え、調査時の調整支援 |
申請から認定までの流れを理解し、各立場で必要な手配を事前に済ませておくことで、調査がスムーズに進みます。
調査の準備と本人・代理人の役割分担
介護認定調査に備える際、本人と代理人それぞれに役割があります。本人は自身の健康状態や生活の困難さを調査員へ率直に伝え、普段の生活や支援が必要な場面を具体的に説明します。家族や代理人は医療・通院状況、服薬内容、特定疾病の有無などを資料やメモで準備し、伝え漏れが無いようにサポートすることが大切です。
調査前に準備することの一例をリストアップします。
-
要介護認定申請書の記入
-
介護保険証、健康保険証の用意
-
診断書や通院記録の整理
-
現状の困り事や支援希望内容のまとめ
代理申請の場合は、委任状や相談記録の控えも必須です。特定疾病による申請では、該当病名や診断基準が明確であるか再確認してください。
認定結果の通知方法と区分変更申請の流れ
認定調査の終了後、自治体から「認定結果通知書」が郵送で届きます。結果には要支援・要介護の各区分や、利用可能な介護サービスの内容・範囲が明記されています。通知を確認後、サービスの利用計画作成や介護保険証の有効期限などもチェックしましょう。
結果に不一致を感じた場合や、健康状態が急激に変化した場合は区分変更申請が可能です。手続きの流れは以下の通りです。
-
区分変更申請書を自治体窓口へ提出
-
新たな調査日程の調整
-
再度認定調査の実施
-
改めて認定審査が行われ、結果が郵送で通知
サービス利用中でも状態が変われば随時手続き可能です。入院・退院など生活環境が大きく変わった場合も忘れず申請を検討してください。
不服申し立ての具体的手順と注意点
認定結果に納得できない場合、行政に対して不服申し立てができます。通知受領後60日以内に、都道府県または指定の審査会へ「不服申立書」を提出する必要があります。必要書類や理由を具体的にまとめ、必要に応じて主治医や支援者の意見書を添付すると効果的です。
不服申し立ての流れは下記の通りです。
- 認定結果の詳細確認
- 不服申立書の作成
- 申立先窓口で提出・受付
- 審査会で再検討・判断
- 結果通知の受領
申請は一度だけでなく繰り返し可能ですが、形式不備や根拠不足がないよう注意しましょう。家族・専門職のサポートを受けながら、適切な準備を重ねることで認定の見直しが期待できます。
申請できる人に関するよくある疑問と誤解、注意すべきポイント
申請できる人に関する誤解のクリアリング
介護保険を申請できる人については、多くの誤解や迷いがあります。申請できる対象者は主に65歳以上の方と40歳から64歳で特定疾病に該当する方です。65歳以上の人は年齢要件のみで申請可能です。40~64歳の場合は、16種類の特定疾病による介護が必要な時に限られます。本人以外にも代理申請が認められており、家族やケアマネジャー、施設職員などが手続きを代行できます。自身の状態や年齢、特定疾病に当てはまるかを確認し、少しでも該当する可能性があれば、迷わず相談することが重要です。
| 申請者 | 条件 | 注意点 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 年齢のみ | 常に申請可能 |
| 40~64歳 | 特定疾病による介護状態 | 疾患が16特定疾病に該当する場合のみ |
| 本人以外(代理人) | 家族等が書類と同意を準備 | 窓口での確認が必要な場合あり |
申請しない場合のリスクとデメリット
介護保険を申請しない場合、必要な介護サービスの利用ができず、家族や本人に大きな負担がかかります。特に突然の入院や認知症進行など、急な介護状態になった際に制度を使えないことは大きなデメリットです。要介護認定を受けていないと、医療や福祉のサポートが受けられず、自費で全てを賄う必要に迫られるケースもあります。また、制度利用開始までには時間がかかる場合があるため、早めの申請が自分や家族を守る手段となります。
-
介護サービスの自己負担増加
-
家族への精神的・経済的負担増
-
適切なサポートや福祉制度の非活用
-
急な状況変化時にサービス利用不可
申請後の給付やサービスの活用時の注意点
介護保険申請後、要介護・要支援認定を受けた場合、さまざまなサービスが利用可能です。サービス利用は認定結果と区分に基づいて計画されるため、ケアマネジャーとの連携が欠かせません。給付の範囲や利用できるサービスには上限や条件があるため、自身の状態や生活に合ったプラン設計が重要です。複数サービスを組み合わせた場合、利用限度額を超えると自己負担が発生します。入院中でも申請・サービス利用が可能なケースがあり、早めの相談をおすすめします。
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 申請後の認定区分 | 要支援1~2、要介護1~5 |
| サービス利用の流れ | ケアプラン作成→サービス事業所と契約 |
| 費用・負担割合 | 原則1~3割負担、限度額オーバーは全額負担 |
| 入院中の申請 | 特例対応可、退院後の利用がスムーズに |
| 代理申請の活用 | 家族やケアマネジャーが代行できる |
細やかな制度や運用方法は自治体によって異なる場合があるため、疑問や不安は速やかに市役所や地域包括支援センターへ相談し、最新の情報を把握しておくことが障害なくサービスを活用するコツです。
介護保険申請に関するFAQを網羅的に解説
介護保険は誰でも申請できるのか?
介護保険を申請できるのは、主に次の2つの対象です。
-
65歳以上の方(第1号被保険者)
年齢のみで申請可能。原因は問われません。
-
40歳から64歳の方(第2号被保険者)
指定された「特定疾病」により要介護や要支援状態にある場合のみ申請が可能です。
年齢条件や特定疾病に該当しない場合は原則として申請できません。対象外となる40歳未満や、特定疾病がない場合は注意が必要です。
特定疾病の詳細と申請条件は?
第2号被保険者が介護保険を利用するには、厚生労働省が定める16種類の「特定疾病」により介護が必要な状態であることが必要です。
主な特定疾病は次の通りです。
| 特定疾病の例 | 解説 |
|---|---|
| 初老期認知症 | アルツハイマー型・レビー小体等 |
| 脳血管疾患 | 脳梗塞や脳出血後遺症 |
| パーキンソン病関連疾患 | 悪性関節リウマチ |
| がん末期 | 末期ガン |
必ず指定の診断書が必要で、診断基準に基づき認定されます。
代理申請する場合の必要書類は?
本人が介護保険の申請を行うことが難しい場合、家族や成年後見人による代理申請が認められています。代理申請を行う際に必要な主な書類は以下の通りです。
-
介護保険被保険者証または健康保険証
-
本人の身分証明書
-
代理人の身分証明書
-
代理申請届出書(自治体指定の様式の場合あり)
-
委任状(必要な場合)
自治体によって多少異なる場合があるため、事前の確認が重要です。
入院中でも申請はできるのか?
入院中の方も要介護・要支援認定の申請は可能です。病院にいる間に申請手続きを進めておくことで、退院後すぐに介護サービス利用が開始できるケースも多くあります。
認定調査は原則として本人のもとへ面接訪問されますが、入院先の医師や看護師との連携のもと行われることが一般的です。
申請後に認定が降りなかったらどうすればいい?
申請後に「非該当」となった場合でも、状況が悪化したり状態が変化した時には再申請が可能です。また、認定結果に納得できない場合は「不服申し立て」ができます。
-
経過観察して再申請
-
認定後30日以内に市町村へ不服申し立て
提出書類や手続き方法は各自治体で案内されています。
申請窓口はどこにある?市役所や相談先の案内
介護保険の申請は【市役所の介護保険課】や【地域包括支援センター】が窓口です。自治体により窓口名は異なりますが、下記のいずれかにて受付されます。
| 申請窓口 | 連絡先・位置例 |
|---|---|
| 市町村の介護保険担当窓口 | 市役所・区役所・町村役場内 |
| 地域包括支援センター | 地域の高齢者向け福祉センターなど |
| 指定居宅介護支援事業所(ケアマネ) | サービス付き高齢者住宅など |
電話やオンライン相談にも対応しています。
申請のタイミングはいつがベストか?
介護が必要だと感じたら、できるだけ早い申請が推奨されます。急激な体調変化や病気発症時、入院直後・退院前などが主なタイミングです。
早期申請をしないとサービス利用開始が遅れることになります。必要に応じて医師やケアマネジャーなどに相談して進めましょう。
申請に必要な書類の揃え方とポイント
申請時は以下の書類を準備しましょう。
-
介護保険被保険者証(65歳以上の方)
-
健康保険証(40~64歳の特定疾病該当者)
-
医師の意見書(後日提出も可)
-
代理申請の場合は委任状や代理人の本人確認書類
提出時には不備がないかチェックが重要です。分からない場合は市役所や地域包括支援センターに相談するとスムーズです。
区分変更や不服申し立ての具体的な流れ
介護度に変化があった場合や認定結果に納得できない場合は、次のような流れで手続きします。
- 状況変化や状態悪化時に区分変更申請書を提出
- 市町村が再調査・医師意見書の再取得を実施
- 結果に不満がある場合は、結果通知から30日以内に「介護保険審査会」へ不服申し立て
適切な資料が必要となるので、ケアマネジャーや専門員に相談しながら進めると安心です。