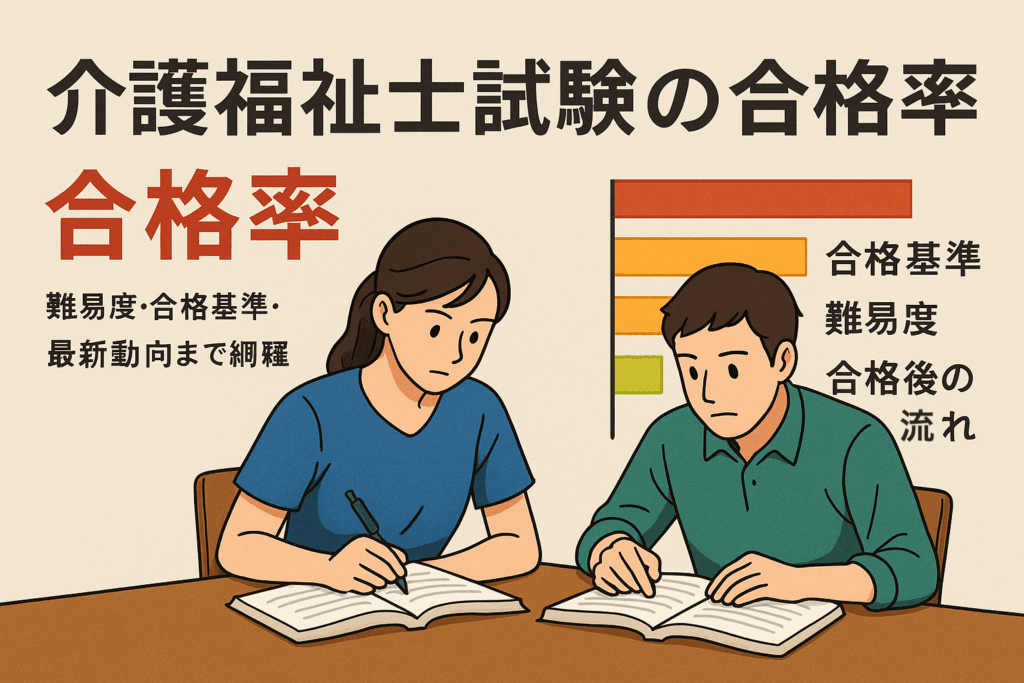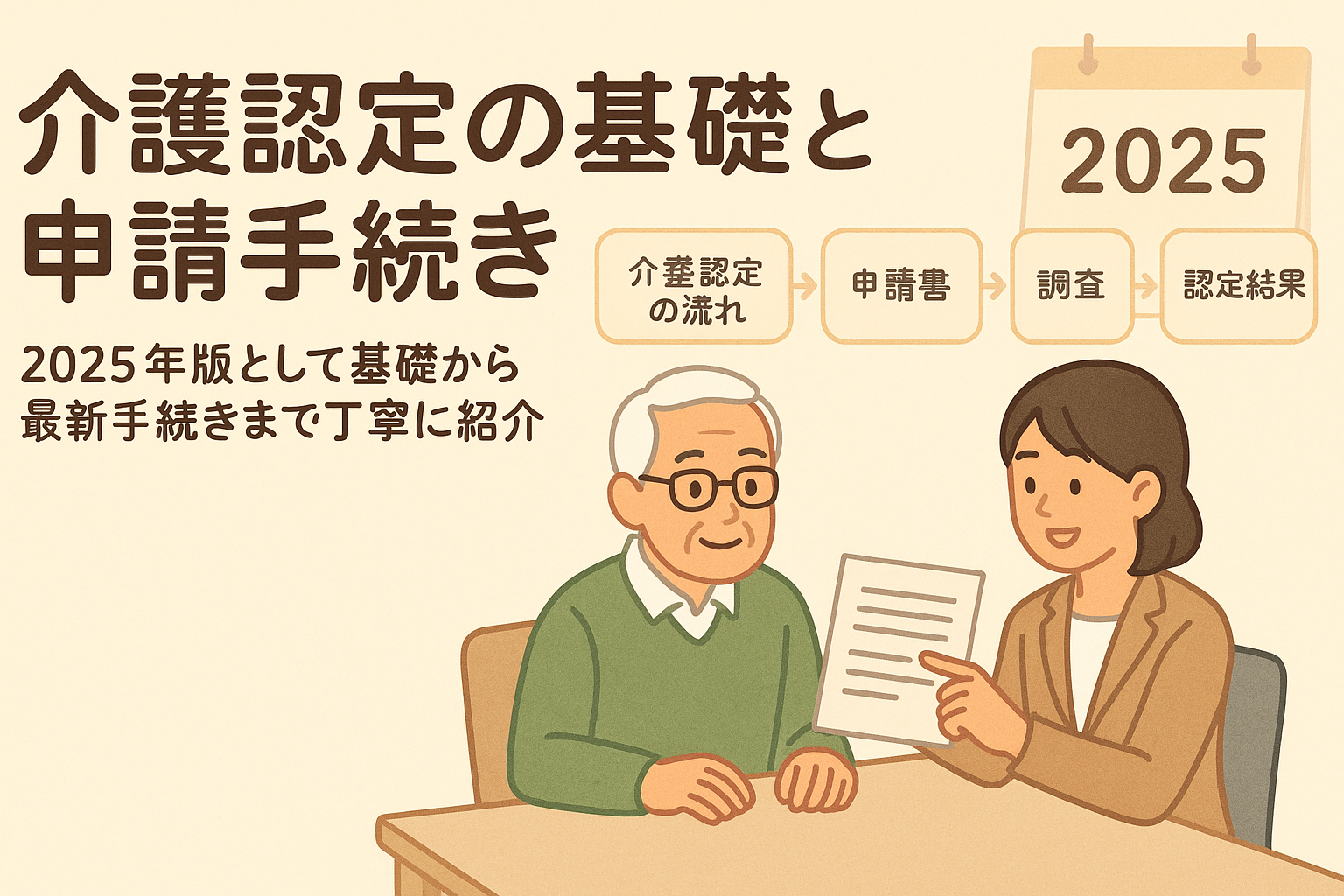2025年1月に実施された「第37回介護福祉士国家試験」。今年の合格率は【78.3%】となり、受験者数【80,106人】のうち、過去3番目に高い合格率を記録しました。毎年数万人が挑戦する中、合格者数や合格基準の変動に「一度で本当に受かるのか」「前年との違いは?」と不安を感じていませんか?
介護福祉士は「国家資格」として信頼性が高く、医療・福祉現場で活躍するうえで資格の有無が大きな意味を持ちます。しかし、実際の合格基準は毎年細かく調整されており、単なる得点だけでなく科目ごとの基準も設けられています。たとえば2025年試験では総得点125点中75点以上、かつ必須11科目で1点以上が条件でした。
「合格者が増えているのはなぜ?」「最新の合格率からどうやって自分の対策を立てればいい?」そんな疑問や不安を持つ方のために、この記事では最新データと公的機関発表の数値をもとに、合格率・合格基準のすべてをやさしく、かつ正確に解説します。
最後まで読むことで、あなたに最も適した勉強ポイントや、数字から見えてくる試験の現実をしっかり把握できます。試験本番を「何となく」で迎えないためにも、正しい情報で今後の準備を始めませんか?
介護福祉士国家試験の合格率の基礎知識と概要解説
介護福祉士国家試験とは何か – 試験の目的と重要性
介護福祉士国家試験は、介護の専門知識と技術、水準の高い実務能力を証明するために設けられています。医療や福祉の現場では、専門職としての資格を持つことが求められ、施設や在宅介護サービスで安心して働くための基盤となります。高齢化社会が進む中で、介護福祉士の役割はますます重要となり、社会的評価やキャリアアップに直結する公的資格です。
国家試験の構造と評価基準の概要説明 – 出題範囲や評価方法を明確に解説する
介護福祉士国家試験の出題範囲は、社会福祉・医学一般・介護技術・人間と社会・こころとからだのしくみなど多岐にわたります。評価方法は全125問のマークシート方式で、マークシート方式により全受験生に公平な判定が行われています。合格基準は、総得点の60%以上(67点)かつ11科目全てで基準点以上を取得する必要があり、バランスの取れた知識が求められます。
合格率の定義と数値の意味 – なぜ注目されるのか
合格率は、受験者全体に対する合格者の割合を示し、毎年の試験難易度や業界の動向を把握する指標です。合格率が高い年は制度改革や出題傾向の変化が影響する場合があり、現役受験者だけでなく、今後受験を考える方にとっても大きな関心事となっています。
公的データと合格率表の見方のポイント – 数値の読み解き方と信頼性の根拠を示す
合格率は厚生労働省などの公的機関が公式発表するため、信頼性が高いことが特徴です。過去10年分の推移を見ることで、年ごとの変動や難易度の傾向を把握できます。特に、合格者数・受験者数・合格率の3点を比較することで、自分の立ち位置を客観的に判断できます。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 84,483 | 73,659 | 87.2% |
| 2024 | 77,187 | 62,282 | 80.7% |
| 2025 | 75,387 | 58,992 | 78.3% |
最新の合格率速報の解説 – 2025年試験の結果を中心に
2025年実施の第37回介護福祉士国家試験では、合格率は78.3%でした。過去10年で3番目に高い結果ながら、前回からやや減少しています。受験者数・合格者数ともに減少傾向ですが、依然として高い水準を維持しており、資格取得のチャンスは広がっています。外国人受験者や学校別の合格率にも注目が集まっており、将来の進路や対策に役立つ各種データの活用が推奨されます。
介護福祉士国家試験の合格率の最新動向と過去推移詳細分析
2025年(第37回)介護福祉士国家試験の受験者数・合格者数・合格率の最新データ完全解説
2025年実施の第37回介護福祉士国家試験では、受験者数75,387人、合格者数58,992人となり、合格率は78.3%となりました。直近数年でみても合格率は比較的高い水準を維持しています。受験生の増減だけでなく、外国人受験者や特定技能枠での受験者増加も特徴です。特に外国人受験者は全体の約10%を占め、その合格率は71.2%と高い水準でした。近年は多様な受験者層が試験に参加しており、制度改革や社会的ニーズの変化が背景にあることが伺えます。
合格率78.3%の背景と数値比較(2021~2025年) – 年度別の変化や特徴を深く分析
過去5年間の合格率の推移は次のとおりです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 2021 | 84,483 | 59,679 | 70.7% |
| 2022 | 82,950 | 60,752 | 73.2% |
| 2023 | 76,857 | 69,688 | 90.7% |
| 2024 | 77,637 | 62,410 | 80.4% |
| 2025 | 75,387 | 58,992 | 78.3% |
合格率が80%を超えた年もありましたが、2025年はやや減少しました。受験者数の減少が影響し、合格基準に達する受験者が安定していることがわかります。
過去10年〜15年における合格率の変動推移とその特徴
2010年代以降、介護福祉士国家試験の合格率は大きな変動を見せています。2011年は60%台でしたが、2018年以降は70~80%台を推移し、2023年には90.7%という異例の高水準も記録しました。合格点は総得点125点中、約60%(67点)前後が基準となっており、年ごとに小幅な変動があります。背景には、試験制度の改正や受験資格の拡大、外国人受験者増加といった社会情勢の変化が複合的に影響しています。
学校別・養成施設別・地域別にみる合格率の違いと傾向 – 多様な分析から現状を可視化
学校別・養成施設別の合格率は、養成校卒業見込み者が9割前後と非常に高く、一般受験者は6~7割とやや低めです。地域による違いもあり、主要都市圏では受験者の増加が目立つ一方、地方では受験者数そのものが減少しています。
| 分類 | 合格率(例) |
|---|---|
| 養成施設 | 91.5% |
| 一般 | 67.8% |
| 外国人 | 71.2% |
これらのデータを踏まえた選択や学習計画が、合格への近道となります。
合格率の推移に伴う試験難易度の変化とその解説
合格率と試験難易度は表裏一体であり、年ごとの基準点設定や出題範囲の変動も影響を与えています。以前に比べて出題傾向がやや幅広くなったものの、合格率は一定水準を維持しています。受験者側の準備状況、教育機関のサポート充実、対策教材の進化も難易度に影響し、近年はしっかりと対策を行えば多くの受験生が合格を目指せる環境です。どの世代・属性の受験生も安心してチャレンジできます。
介護福祉士国家試験の合格率に関わる合格基準・配点と試験難易度の詳細
合格基準点の設定基準と変遷(過去回との比較)
介護福祉士国家試験の合格基準点は、総得点125点中60%以上(例:75点前後)が目安です。これは各回ごとに出題難易度を考慮して補正される場合があり、年度ごとに若干の変動があります。特に近年は受験者層の多様化や問題の難易度調整により合格基準の見直しも行われ、直近の第37回試験では67点が基準となりました。過去10年を振り返ると、合格点の推移は下記のように安定しています。
| 回数 | 合格基準点 | 受験者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第37回 | 67点 | 75,387 | 78.3% |
| 第36回 | 71点 | 84,032 | 83.4% |
| 第35回 | 74点 | 87,813 | 83.5% |
| 第34回 | 76点 | 87,233 | 72.3% |
直近では80%を超える高水準が続いた後、やや難化傾向もみられます。合格基準の変遷は毎年発表されるため、必ず最新情報を確認しましょう。
各科目別配点と必須科目の合格条件の詳細 – 詳細な算出方法や注意点
介護福祉士国家試験は「合計点」と「科目ごと」の2つの合格条件があります。
-
総得点基準:筆記125点満点中における合格基準点以上の得点(例:67点以上)
-
科目別基準:必須11科目群すべてで1点以上の得点
特に注意すべき点は、いずれかの科目で0点の場合、総得点が基準に達していても不合格になることです。科目ごとのバランスも求められるため、得意分野だけでなく全科目をまんべんなく対策する必要があります。各科目の配点例と合格条件をまとめました。
| 科目 | 配点 | 合格条件 |
|---|---|---|
| 人間の尊厳と自立 | 5 | 1点以上 |
| 介護の基本 | 10 | 1点以上 |
| 医療的ケア | 7 | 1点以上 |
| 社会の理解 | 16 | 1点以上 |
| その他7科目 | 合計87 | 各1点以上 |
配点の詳細は年度によって変動する場合があるため、事前に最新の「試験案内」を確認しましょう。
難易度評価の観点と受験生の実感・心理的影響
最近の介護福祉士国家試験は全体の合格率が高いことから「やさしい」との声がある一方、受験者によると科目別のバランスや初見問題の出題に「難化」と感じたケースも少なくありません。特に30代~50代の社会人経験者や転職を考える方が多く受験しており、各自のバックグラウンドによって実感には幅があります。
-
出題範囲が広く、暗記だけでなく実務経験・理解型の問題も多い
-
合格基準の厳格化や科目別条件で緊張感が高まる
-
試験直前の「合格点調整」や年度ごとの変化に不安を感じる受験生もいる
受験前の十分な準備と最新動向への対応が重要です。
外国人受験者や実務者研修ルートの合格状況と特徴
外国人受験者や実務者研修ルートからの受験者も年々増加しています。第37回試験では、外国人受験者の合格率は全体平均とほぼ同程度、74~80%前後で推移しており、近年の支援制度や日本語教育の拡充も後押ししています。
-
外国人実習生や特定技能制度での就業経験者の合格率も高い傾向
-
実務者研修経由での合格者は、現場経験を活かして筆記試験にも強い
学校別合格率では、多くの専門学校や大学、養成機関ごとに差が出ることもあり、自校の合格実績をチェックする受験者が増えています。受験方法やルート選びが合格率に大きく影響するため、自身に合った進路選択がポイントです。
介護福祉士国家試験の合格率を考える社会背景と制度の関係性
高齢化社会による介護職需要と合格率の関連性分析
日本の高齢化が進行する中、介護職への需要は年々高まっています。この動向は介護福祉士国家試験の合格率にも密接に関係しています。高齢者人口の増加に伴い、介護現場には多くの人材が必要となり、国家資格を持つ介護福祉士の採用が重視されています。厚生労働省の発表によると、介護福祉士国家試験の合格率は近年上昇傾向にあります。これは、現場の人手不足を背景とした資格取得者の増加と、就業環境の改善努力が反映された結果です。
試験の受験者層も広がっており、従来の新卒者だけでなく社会人や外国人の受験も増加しています。これにより、介護の専門性や質の向上が求められる一方で、多様な人材確保の必要性が高まっています。
資格制度の改正と試験合格率への影響
介護福祉士国家試験の合格率推移を見ると、制度改正がいかに合格率へ影響を与えているかが分かります。従来、実務経験ルートと養成施設ルートが存在し、それぞれに合格率の差が見られましたが、近年では国家試験一本化や実務者研修の必須化など制度変更が進みました。
制度改正後の合格率を表にまとめます。
| 年度 | 合格率(%) | 主な制度変更 |
|---|---|---|
| 2015年 | 61.0 | 実務経験ルートの筆記試験導入 |
| 2023年 | 83.3 | 受験資格要件等の見直し |
| 2024年 | 85.5 | 必須科目の得点基準変更 |
| 2025年 | 78.3 | 試験出題範囲見直し・多様な受験者層 |
これにより、一定水準以上の実務知識や技能を持った受験者が増加し、合格率の安定や向上につながっています。外国人受験者へのサポートや適応も進められ、介護現場の国際化も進行中です。
受験者数の増減要因と介護業界の動向
介護福祉士国家試験の受験者数および合格者数は、社会状況や業界動向の影響を強く受けます。
以下の要素が主な増減要因です。
-
介護業界の求人需要拡大
-
外国人労働者の受け入れ拡大(特定技能やEPA枠など)
-
受験資格変更や研修課程の必須化
近年、特定技能介護や在留資格の多様化により、外国人の介護福祉士国家試験受験者が大幅に増加しています。実際に養成施設等別の合格率も発表され、学校別合格率の傾向も注目されています。
また、介護職は資格取得を通じてキャリア形成がしやすいという利点もあり、医療や看護師分野とも連携が進んでいます。今後も試験制度の変化や業界ニーズを踏まえた受験動向が継続して注視されます。
介護福祉士国家試験の合格率から読み解く受験者層の実態と多様性
年代別・性別・職種別 合格率と受験傾向の分析
介護福祉士国家試験の合格率を分析すると、受験者層の多様性が明らかです。年代別では20代の合格率が高く、特に専門学校や大学・短大卒業の直後に受験する人が目立ちます。30〜40代は実務経験を積みながら資格取得を目指す傾向が強く、ライフステージに応じた受験パターンが特徴です。
性別でみると、女性受験者が全体の約7割を占めており、合格率にも大きな差はありません。男性も年々増加しており、介護分野への関心の高まりがうかがえます。職種別では、介護職員が最も多く、他には看護師・ヘルパーや医療・福祉関連職の受験も一定数存在します。
| 年代 | 合格率(推定) | 備考 |
|---|---|---|
| 20代 | 約80% | 学校卒業直後の受験者が多い |
| 30代 | 約75% | 現場経験者が主体、家庭や仕事と両立 |
| 40代 | 約72% | 実務を活かしキャリアアップを目指す傾向 |
| 50代以上 | 約68% | 転職や資格取得による再挑戦が見られる |
職種別の傾向は、働きながら勉強する層もしっかり合格を目指している点が特徴です。
外国人受験者の割合と合格実績・支援体制
近年、外国人受験者が増加傾向にあります。最新では外国人受験者が全体の1割近くを占めており、合格率も70%前後で日本人受験者と大きな差はありません。特定技能や技能実習などを活用した外国人介護職の増加が背景にあります。
支援体制の一例として、多言語での試験案内や、特別な研修・サポートプログラムが整備されています。日本語の理解度を高めるための講座や、現場実習中のフォローも進められており、外国人の資格取得を後押ししています。
| 年度 | 外国人受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 第35回 | 約8,500 | 約6,100 | 71.7% |
| 第36回 | 約9,200 | 約6,900 | 75.0% |
| 第37回 | 約9,700 | 約7,100 | 73.2% |
このように外国人資格取得希望者も高い水準で合格しており、今後さらに支援と需要が拡大することが予想されています。
一発合格率や複数回受験者の成績傾向
一発合格率は全体で約60〜65%と高く、初回受験で合格する人が多いのが特徴です。養成施設や学校別のサポートがある場合、さらに一発合格率が上がる傾向があります。過去に不合格となり複数回挑戦する受験者の場合、経験値が活かされ2回目以降の合格率も70%以上と着実に上昇します。
一発合格を目指す受験者に有益なのが、実践的なカリキュラムと早い段階での対策です。複数回受験者は自身の弱点を的確に振り返り、効率的な勉強法に切り替える傾向が見受けられます。
| 回数 | 合格率 | 特徴 |
|---|---|---|
| 1回目 | 62% | 学校や養成施設在学中の受験者が有利 |
| 2回目 | 72% | 経験と学び直しで合格度が上昇する |
| 3回以上 | 76% | 諦めずに継続受験する姿勢が成果に直結 |
このように対策を重ねることで、幅広い年齢・バックグラウンドの受験者が合格を実現しています。
介護福祉士国家試験の合格率データを活かした最適な試験対策と勉強法
最新の介護福祉士国家試験では、合格率が約78%と高い水準を維持しています。近年の合格率推移を確認しながら、自分に合った学習計画を立てることが合格への近道です。特に第37回(2025年)の合格点や出題傾向を把握し、効率的に勉強を進めましょう。合格実績が高い養成施設出身者や学校別合格率にも注目し、自分に適した学習環境を選ぶこともポイントです。
合格者の多くは、過去問や模擬テストを活用し、出題傾向を分析して弱点分野を補強しています。また、外国人受験者向けの対策や特定技能の関連情報も増えており、多様なニーズに対応した学習法の工夫が重要です。
合格点予想と過去問活用法 – 合格率推移から導く学習戦略
合格点は例年67点前後(125点満点中)が目安とされています。過去の合格点や問題傾向を分析することで、出題内容の重点分野が把握しやすくなり、試験対策の精度が上がります。
過去10年の合格率推移
| 年度 | 合格率(%) | 合格点(目安) |
|---|---|---|
| 2025年 | 78 | 67 |
| 2024年 | 80 | 68 |
| 2023年 | 84 | 68 |
| 2022年 | 72 | 68 |
| 2021年 | 72 | 67 |
過去問活用のポイントリスト:
-
本試験と同レベルの問題を繰り返し解く
-
過去問の正答・誤答分析で弱点を可視化
-
よく出る分野、難問分野を重点的に演習
合格率変動による難易度対策の工夫
近年の合格率は70〜80%台で推移していますが、年によって難易度差や合格点の変動が見られるのも特徴です。難易度が高まる年でも、出題傾向に合わせた対策があれば十分に合格を目指せます。
難易度対策のポイント:
-
合格基準点と各分野の得点バランスを意識
-
新傾向問題や必須問題の早期対策
-
最新試験の公式発表内容を随時チェック
受験者の成功体験・失敗談から学ぶ効果的なアプローチ
多くの合格者は、計画的な勉強と精神的な余裕づくりが合格の秘訣と語っています。また、焦って無理なスケジュールを設定したり、苦手科目を放置したままだと不合格となるケースが少なくありません。
受験者の声から得られるアドバイス:
-
「毎日30分でもコツコツ続けたのが合格につながった」
-
「直前期は模試や過去問で本番形式に慣れるのがおすすめ」
-
「わからない分野はネットや研修で早めに解消した」
このような経験を参考に、自分に合った無理のない勉強計画を構築し、合格率が高い年でも油断せず着実に得点を積み重ねていくことが大切です。
介護福祉士国家試験の合格率にまつわるよくある質問 見逃せないポイント集
合格率は年度によって大きく変わる?
介護福祉士国家試験の合格率は年によって変動します。例えば2024年度の第37回介護福祉士国家試験の合格率は78.3%でしたが、過去10年の中では70%台前半から80%台前半まで幅があります。直近5年の推移は以下の通りです。
| 年度 | 合格率 |
|---|---|
| 2021 | 71.0% |
| 2022 | 72.3% |
| 2023 | 84.4% |
| 2024 | 88.3% |
| 2025 | 78.3% |
このように毎年の合格率には差があり、試験問題の難易度や受験者層によって上下しています。過去20年の推移をみると、70〜80%台が標準的な水準と考えて良いでしょう。
合格点は毎年どのように決まるのか?
合格点(合格基準)は、総得点が60%を超えることが目安となっています。第37回では全125点中67点以上が合格点でした。過去10年の推移を見ても「総得点の60%前後」ですが、試験の難易度や問題内容により「補正」される場合もあります。
合格点に到達するには以下の条件が必要です。
-
総得点で基準点(約60%)以上
-
必須問題(11科目)すべてで1問以上正解
また、回によってやや上下があるため直近データの確認が重要です。
外国人受験者の合格率は一般と比べどうなのか?
外国人受験者の合格率は年度や制度によって異なりますが、全体の合格率よりやや低い傾向にあります。2025年の第37回試験では、外国人受験者のおおよその合格率は約60%前後とされています。
理由は日本語能力や介護現場での経験年数に違いがあるためです。ただし、2020年代以降は教育体制が整備されつつあり、合格率は徐々に高まる傾向です。
学校別の合格率はどの程度参考になるか?
学校別合格率は各養成校の公式サイトや厚生労働省で公表されており、指標のひとつにはなりますが、受験者数や学生の進路、サポート体制などにも左右されます。以下の点で参考になります。
-
指導体制やカリキュラムの違い
-
実習や模擬試験回数
-
勉強支援の有無
複数の学校データを比較し、自分に合った学習環境なのかを判断する材料の一つとして活用するのがおすすめです。
実務者研修を経た受験者の合格率は?
実務者研修修了者の合格率は高めで、一般的に80%以上といわれています。実務経験を体系的に学び直せるため、理解が深まりやすいのが理由です。研修後の受験は合格点に到達しやすく、過去のデータでも合格率の上昇がみられます。
主なポイント
-
現場経験に加えて知識を整理できる
-
試験傾向や出題範囲を把握しやすい
-
不明点を講師に相談できる
実務者研修を経た上での受験が有効です。
独学や通信講座での合格可能性は?
独学や通信講座でも合格を狙うことは十分可能です。ただし、過去問の活用と効率的な学習計画が不可欠です。近年の受験者の中では、以下の準備を行うことで独学でも高い合格率を保っています。
-
過去10年分の過去問題集の徹底反復
-
最新試験傾向のチェック
-
合格基準の再確認
-
模擬試験やオンライン講座の活用
限られた時間でも正しいポイントを押さえて学習を進めることで、十分に合格点へ到達できます。
介護福祉士国家試験の合格率と受験後の手続き・キャリア形成への影響
介護福祉士国家試験の合格率は毎年高水準で推移しており、近年は70~80%台を記録しています。2025年実施の第37回では78.3%と、依然として多くの受験者が合格しています。合格率の高さは、福祉・介護分野への新規参入者や経験者のステップアップを後押ししており、外国人受験者や学校別・養成施設等ごとの合格率動向も注目されています。
合格後の手続きや求人市場での需要、資格取得後のキャリア形成にもこの合格率が大きく関わってきます。合格した後は速やかな登録手続きが求められ、実際に仕事やキャリアにつなげるための情報収集も重要です。試験合格後の流れや各種申請の注意点、就業段階でのポイントも理解しておく必要があります。
合格後の申請手続きプロセスと必要書類
介護福祉士国家試験に合格すると、実際に「介護福祉士」として登録し、業務を行うためには以下のステップを踏む必要があります。
| 手続きの流れ(一例) | 必要書類(一部抜粋) |
|---|---|
| 1. 合格証明書の受領 | 合格証明書、本人確認書類 |
| 2. 登録申請書の提出 | 登録申請書、住民票の写し |
| 3. 登録手数料の納付 | 振込証明書など |
| 4. 登録完了・証書交付 | (手続き後に交付) |
必要書類や詳細な流れは年度や条件により異なるため、厚生労働省や指定登録機関の公式サイトで最新情報を確認しましょう。
登録が完了すると介護福祉士として公的に認められ、各種施設や在宅サービスなど幅広い現場で専門職として働くことが可能になります。速やかな申請と必要書類の事前準備が円滑なキャリアスタートにつながります。
資格取得後のキャリアパス選択肢と合格率の関係
介護福祉士資格取得後は、多様なキャリアパスが選択できるのが大きな特徴です。
-
介護施設や福祉施設での専門職としての勤務
-
医療現場との連携やリーダー職への昇進
-
医療・看護領域やケアマネジャー、相談員など他職種へのステップアップ
-
施設運営や管理職へのキャリアアップ
-
外国人の場合、在留資格の更新や就労ビザの取得・永住申請への展開
合格率の高さは、介護福祉士が現場で求められている資格であることを示しており、求人動向やキャリア形成のチャンスを広げています。また、資格取得者は給与や待遇面で優遇される傾向があり、長期的なキャリア安定にも資する重要な資格といえます。
合格率を踏まえた受験と就職活動の最適タイミング解説
介護福祉士国家試験の合格発表は例年3月に行われるため、その後の就職・転職活動や施設選びのタイミングが重要です。
-
合格発表直後は求人が増加する傾向があり、就職に有利
-
合格証の登録完了後に正式な求人応募・内定受諾が可能
-
学校別や地域別の合格率情報を参考に、進学先や受験対策を検討
下表は一般的なスケジュール例です。
| 年度・タイミング | 主な活動 |
|---|---|
| 1月 | 国家試験実施 |
| 3月 | 合格発表・手続き開始 |
| 4〜6月 | 求人応募・新規採用が活発化 |
合格率が安定して高いため早期の受験準備がしやすく、最適なタイミングでキャリアをスタートさせることができます。受験・合格・登録・就職活動を計画的に行うことで、幅広いキャリア形成が可能となります。